ポスティングシステムとは?
ポスティングシステム(posting system、入札制度)は、NPBに所属する選手がフリーエージェント(FA)権を取得せずにMLBなどの海外リーグへ移籍するための制度です。
選手が移籍を希望した場合、所属球団がその申請を承認し、NPBを通じてMLBにポスティングを申請します。
申請後、MLBの全30球団が選手と交渉する権利を得られ、45日間の交渉期間内に契約が成立すれば、移籍先のMLB球団からNPB球団へ譲渡金(移籍金)が支払われます。
現行制度では、譲渡金の計算方法が契約総額に応じて以下のように定められています(2024年時点)
契約総額2500万ドル以下:20%
2500万ドル超~5000万ドル:20%(最初の2500万ドル)+17.5%(残額)
5000万ドル超:20%(最初の2500万ドル)+17.5%(次の2500万ドル)+15%(残額)
この制度により、選手は若いうちにMLB挑戦の機会を得られ、NPB球団は選手の保有権を手放す代わりに金銭的補償を受けられます。
過去にはイチロー(2000年)、大谷翔平(2017年)、山本由伸(2023年)などがこの制度を利用してMLBへ移籍し、大きな成功を収めています。
旧ポスティングシステムと現行制度の違い
旧ポスティングシステム(1998年~2012年)では、MLB球団が入札を行い、最高額を提示した球団が選手との独占交渉権を得る仕組みでした。
例えば、松坂大輔(2006年)の場合、ボストン・レッドソックスが約5111万ドルの入札額を提示し、交渉権を獲得しました。
しかし、この方式では選手に選択権がなく、希望する球団や地域でプレーできない可能性がありました。
また、高額入札が可能な資金力のある球団に有利で、経済格差が交渉の公平性を損なう問題が指摘されていました。
現行制度(2013年以降)は、入札制を廃止し、譲渡金の上限を2000万ドル(2018年以降は契約総額に応じた計算)に設定しました。
これにより、すべてのMLB球団が選手と交渉可能となり、選手は希望する環境や契約条件を考慮して移籍先を選べるようになりました。
選手にとってはFAに近い自由度が確保された一方、NPB球団にとっては譲渡金が制限されるため、経済的メリットが限定的になる課題が生じています。
ポスティングシステムの問題点
ポスティングシステムには、以下のような問題点が指摘されています。
これらは球団、選手、さらには日米間の野球文化の違いに起因するものです。
1. 球団側のデメリット:譲渡金の上限問題
現行制度の最大の問題は、譲渡金の上限が設定されていることです。
過去の例では、ダルビッシュ有投手(2012年)のポスティングでテキサス・レンジャーズが約5170万ドルの入札額を支払いましたが、現行制度では上限が2000万ドル(または契約総額に応じた金額)に制限されています。
このため、NPB球団は選手の市場価値に見合った補償を得られないケースが増えています。
例えば、田中将大投手(2013年、楽天イーグルス)のポスティングでは、2000万ドルの譲渡金でニューヨーク・ヤンキースへ移籍しましたが、当時の市場価値を考えると、旧制度であれば5000万ドル以上の入札額が期待された選手でした。
この上限設定は、特にスター選手を輩出するNPB球団にとって大きな経済的損失となり、「不平等だ」「日本が軽視されている」との批判がNPB側から上がっています。
2. 日米間の制度的不均衡
ポスティングシステムは、NPBからMLBへの移籍にのみ適用される一方、MLB選手が他リーグに移籍する際には同様の制限がありません。
例えば、MLB選手がKBO(韓国プロ野球)やNPBに移籍する場合、移籍金の制限はなく、球団間の交渉で金額が決まります。
この非対称性が、NPB側から「不公平」と見なされる要因となっています。
NPB球団は、選手育成に多額の投資を行っているにもかかわらず、ポスティングによる補償が限定的であるため、若手選手の早期流出を防ぐインセンティブが働きにくい状況です。
3. 選手の選択肢とリスク
選手側にとっては、現行制度は旧制度に比べてメリットが大きいと言えます。
複数球団との交渉が可能になったことで、選手は年俸やプレー環境、チームの競争力などを比較し、自分に最適な選択ができます。
しかし、MLBへの移籍は大きなリスクも伴います。言葉や文化の壁、競争の激しさ、契約の不安定さなど、適応できずに苦労する選手も少なくありません。
また、25歳未満の選手は国際アマチュア選手契約の制限を受けるため、大谷翔平(2017年)のように、市場価値に比べて低額な契約で移籍せざるを得ないケースもあります。
4. 出戻り選手の影響
2024年には、MLBでの活躍が期待された選手がNPBに復帰するケースも見られました。
例として、筒香嘉智選手が横浜DeNAベイスターズに復帰したことが挙げられます。
筒香選手は2019年にポスティングでタンパベイ・レイズに移籍しましたが、MLBでの出場機会が減少した後、2024年にNPB復帰を決断しました。
このような「出戻り」は、ポスティングシステムが選手に海外挑戦の機会を提供する一方、MLBでの成功が保証されない現実を浮き彫りにします。
NPB球団にとっては、復帰選手が経験や知名度を還元してくれるメリットがある一方、若手選手の出場機会が減る可能性も課題として挙げられます。
2024年のポスティング事例と動向
2024年のポスティングシステムを巡る主な事例として、以下の選手の動向が注目されました。
若手投手の移籍:2023年末から2024年初頭にかけて、山本由伸(オリックス・バファローズ)がロサンゼルス・ドジャースと12年総額3億2500万ドルの大型契約を結びました。
この際、オリックスは契約総額に基づく譲渡金(約5060万ドル)を受け取りましたが、山本の価値を考えると、旧制度であればさらに高額な補償が期待された可能性があります。
中堅選手の挑戦:2024年には、複数のNPB中堅選手がポスティングを申請し、MLB球団との交渉に臨みました。例として、救援投手や内野手が中小規模のMLB球団と契約を結ぶケースが見られ、選手の選択肢が増えた現行制度のメリットが発揮されました。
復帰選手の影響:前述の筒香選手のように、MLBでの挑戦を経てNPBに復帰する選手が増えたことで、ポスティングシステムのリスクとリターンが改めて議論されました。復帰選手はNPBの観客動員やチームの競争力向上に貢献する一方、若手選手の育成とのバランスが課題となっています。
今後の展望と改善案
ポスティングシステムの問題点を解決するには、日米間のさらなる協議が必要です。
今後の改善に期待する3つのポイント
譲渡金の柔軟化:譲渡金の上限を撤廃し、選手の市場価値に応じた入札を認めることで、NPB球団の経済的損失を軽減できます。ただし、選手の選択権を損なわないよう、複数球団との交渉権は維持する必要があります。
日米間の対等な制度設計:MLBから他リーグへの移籍にも同様の譲渡金制度を導入し、日米間の不均衡を解消することが求められます。これにより、NPB球団の交渉力が強化され、若手選手の育成意欲が高まるでしょう。
選手サポートの強化:MLB挑戦を希望する選手に対し、言語や文化適応のサポートプログラムを提供することで、移籍後の成功率を高められます。NPBとMLBが共同でこうした支援を構築するのも一案です。
復帰選手の活用:出戻り選手の経験を若手育成やファンエンゲージメントに活かす仕組みを整備することで、ポスティングシステムのリスクをポジティブな機会に変えられます。
ポスティングシステムは、NPB選手がMLBで活躍する夢を叶える架け橋である一方、譲渡金の上限や日米間の制度的不均衡など、解決すべき課題を抱えています。
2024年の山本由伸の大型移籍や筒香嘉智のNPB復帰は、制度のメリットとリスクを改めて浮き彫りにしました。
選手の選択肢を尊重しつつ、NPB球団の経済的利益を確保するバランスの取れた制度改革が求められます。
今後も、日米野球界の連携とファンの声が、ポスティングシステムの進化を後押しするでしょう。

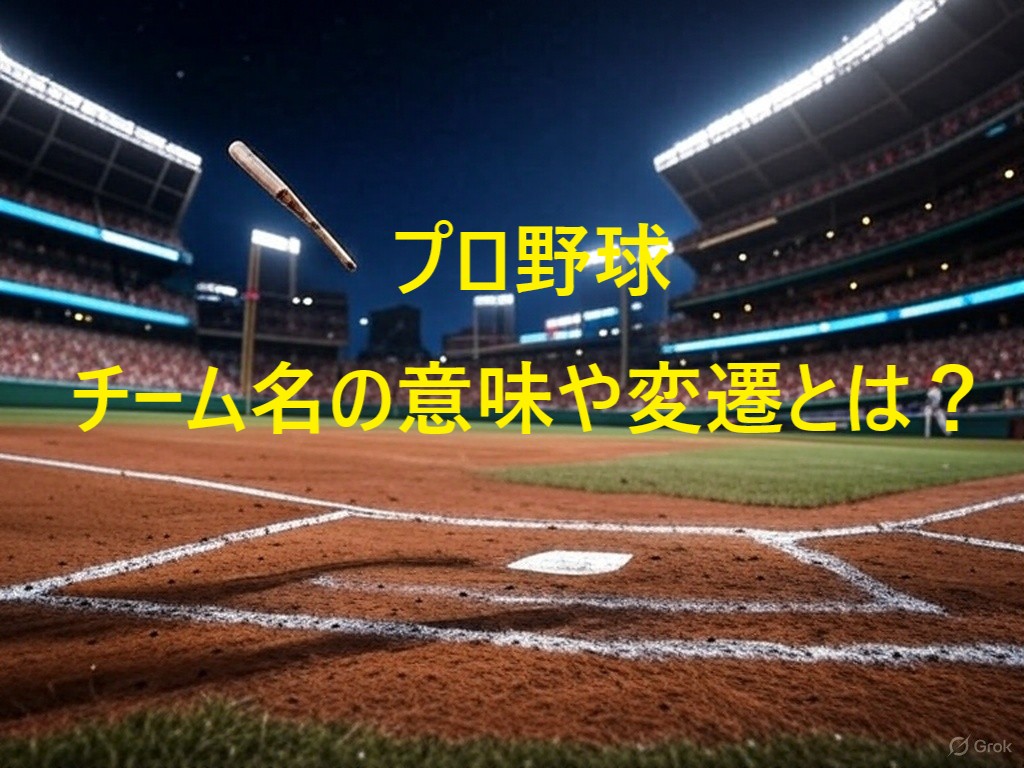
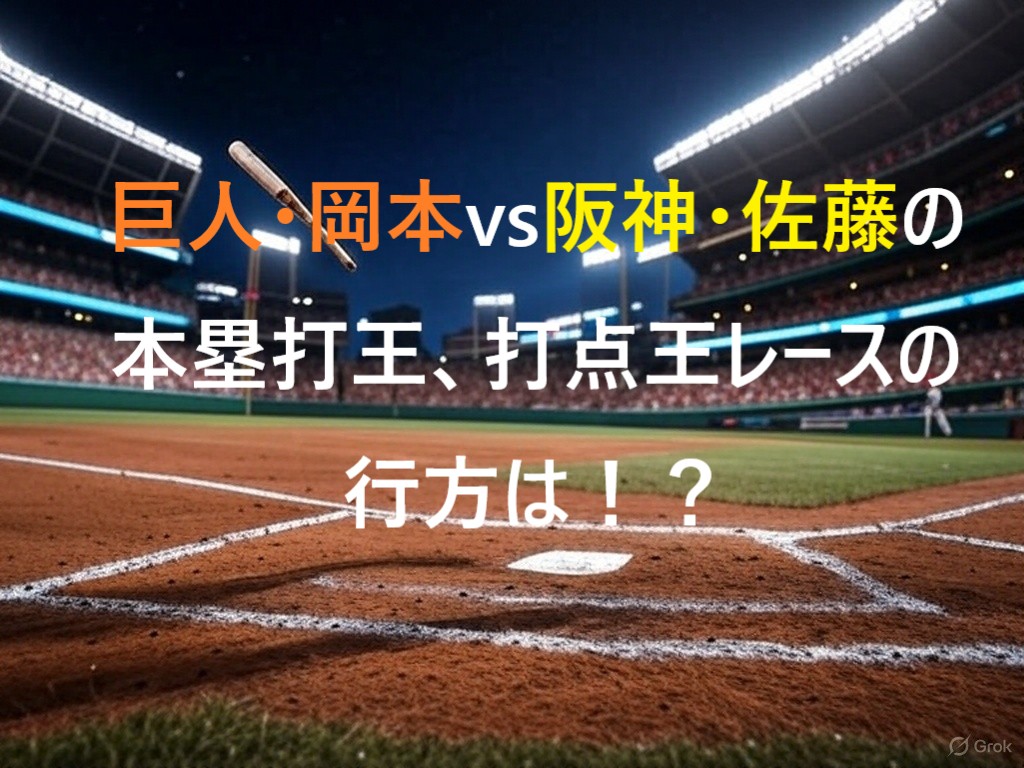
コメント